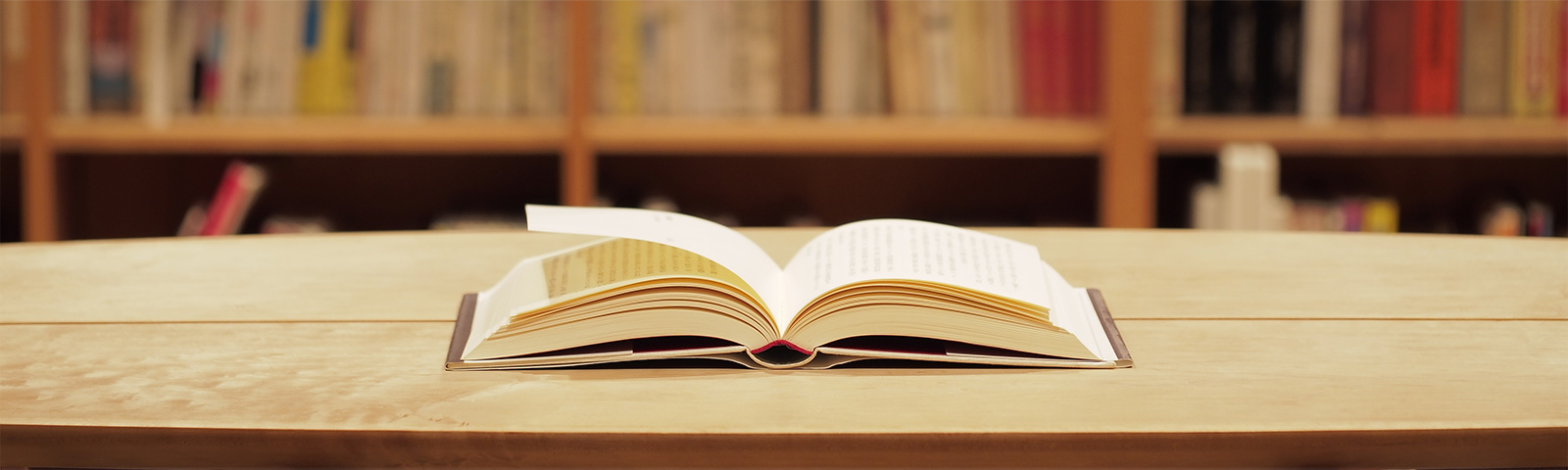読み物の小部屋
きまぐれ本棚
My Bookshelf
芳野香が勝手に「すてき」「おすすめ」と思った本の紹介です。
「すてき」とは言えないけれど「資料的価値あり」「興味があるなら読みやがれ」という本もちょっと混ざっていますが、あしからず。
解剖学関連
骨格 (ビジュアル博物館)
子供向けの写真でつづられたシリーズの1冊。簡潔な説明文は大人にも響く。
プロが教える 筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト事典
スタジオのレッスンや講座、大学院の授業でも使用している1冊。一つ一つの筋肉の位置や名称だけでなく、身体を立体として認識するのを手助けしてくれる1冊。
以下「〇単」シリーズは、身体部位の名称(単語)を学ぶための書籍だが、語源なども説明されているので読み物としても面白いかも。
骨単―語源から覚える解剖学英単語集
肉単―語源から覚える解剖学英単語集・筋肉編
臓単―語源から覚える解剖学英単語集・内臓編
脳単―語源から覚える解剖学英単語集・脳神経編
アーユルヴェーダ&ヨーガの身体
インドの生命科学 アーユルヴェーダ
ある程度総合的にアーユルヴェーダのことを知りたい、という方に手に取っていただきたい1冊。
流水りんこのアーユルヴェーダはすごいぞ~!
インドのアーユルヴェーダ治療院での著者の体験をベースに、面白く楽しく漫画で紹介されています。
アーユルヴェーダ治療院のデトックスレシピ
スリランカの治療院で提供されている食事レシピ集。治療といっても病気の方が入院するだけでなく、体調を整えるために入院することも多いそう。珍しいメニューもいろいろ。
アーユルヴェーダ食事法
食事の理論とレシピが紹介されている本。日本の食事へのアレンジアイデアも掲載されています。
アーユルヴェーダ健美食
食材別に分類や効果などが掲載されていて作りやすいメニューもたくさん。こちらに載っている「ヒーングアシュタチュールナン」は個人的常備品。
黄金のアーユルヴェーダ・セルフマッサージ
朝の習慣としておすすめのオイル・マッサージ。「どこから、どのくらい、どうしたらいいの?」という方は一度手に取ってみるとイメージがわきやすいかと。
図説マルマ
「マルマ」は「急所」にして「救所」。のちに「チャクラ」として概念化されていきますが、具体的に身体に存在する部位です。普段のストレッチやヨーガに取り入れてみて、筋力とは異なる身体からのパワーを感じてみるのも面白いと思います。
メディカルヨガ―ヨガの処方箋
特定の症状に対しヨーガ(アーサナ)でアプローチするアイデアがたくさん掲載されています。
「かたち」「認識」「ことば」でとらえる世界
大自然のかたち
感覚的に「美しい」それでいて「安らぐ」と感じるものの中には、ある法則性があるようです。ビジュアル絵本としても楽しめる1冊。
シンボルの世界
ひとは見えるもの・体験していることのすべてを「わかる」ととらえられるわけではありません。自身の既存の概念や都合に合わないことを「みえない」「わからない」とします。だけどなんだか気にかかる…そんな時人は「シンボル」を通して自分が感じていることを理解する、ということがあります。この本では様々な代表的なシンボルの意味するところを説明しています。イラストも美しい1冊。
シークレット・コード
かたちに潜む規則性を「コード」として紹介している1冊。
code―text and figure
普段見慣れている模様や図像も実は「コード」。内容のみならず、書籍そのものの作りも楽しい1冊です。
MOVE この自然な動きが脳と体に効く
生物として人間として「まとも」に生きることが新鮮に感じられるということは、「あたりまえ」から遠ざかる(凌駕?)ことを「進歩」だと思って頑張ってきたよなー、近代人類!と思ったりするのです。
理論派の方がセルフブラック企業な自分の中の「あたりまえ」を変えたいときに手に取ることを進めたい1冊。
パワーか、フォースか
最初にこの本のタイトルを見たときは「ジェダイ?スター・ウォーズ本?」と思いましたが、さにあらず。この「フォース」は「強いる」という意味です。
レッスンでお会いする人の中には活動・努力の量も多いのに「不満」「不足」「不幸」という感覚から抜け出せない人がいます。この場合の「努力」はたいてい「フォース」。
人の心をひっかき続ける心の問題をキネシオロジー(身体行動学)の視点から書いた1冊。